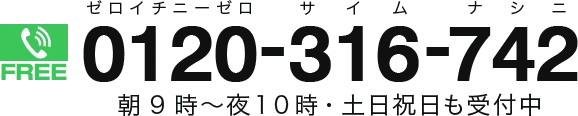民事再生法とは?メリット・デメリットや申請の方法を弁護士が解説

※現在、アディーレ法律事務所は法人に向けた民事再生のご相談・ご依頼を受け付けておりません。個人で民事再生を検討している方は「個人再生」のページをご覧ください。
「民事再生なら事業を継続できるみたいだけど、どうやって申請すればいいんだろう?」
事業の継続を図りつつ、借金を減額するための制度を定めているのが「民事再生法」です。
一方で、事業を継続しつつ借金を減らす制度は、民事再生以外にも「会社更生」もあります。
本ページで、民事再生のメリット・デメリットや、会社更生との違いを知り、ご自身にとってより最適な手続を行いましょう。
民事再生法とは債務者の事業を再建するための法律

日本の倒産制度には、会社の解散を目的とする「清算型」(主に「破産」や「特別清算」)と、会社の継続が目的となる「再建型」の2つがあります。
民事再生法は、経済的に困窮する事業者の経営を立て直すための法律として、再建型の法律に分類されます。
再建型の法律には、「会社更生法」もあります。会社更生は、どちらかというと大規模な企業向けの制度で、手続も複雑です。民事再生と会社更生の主な違いは、のちほどご説明します。
中小企業が裁判所を使って事業立て直しを図る際には、民事再生が用いられるのが一般的です。
民事再生法における再建手続のパターン
民事再生法における再建手続は、主に次の3パターンに分類できます。
- スポンサー型
- 自力再建型
- 清算型
それぞれについて説明します。
スポンサー型
スポンサー型とは、メインバンクや同業他社、再生ファンドなどのスポンサーから借入をしたり出資を受けたりすることにより借金を返済し、再建を図る方法です。
経営状況の悪化で取引先との信頼関係が失われている場合、安定した収益を確保することが困難です。そのため、このあとご説明する「自力再建型」は難しくなります。
しかし、強力なスポンサーが付けば、再び取引先との信用を回復することができ、再建を図れる可能性が高まります。
ただし、この方法を採ることができるのは、再生する会社において魅力的な技術力があるなど、スポンサーにとって魅力的な要素がある場合に限られます。自社の強みをきちんと理解して、スポンサーにアピールできるかが鍵になるでしょう。
自力再建型
自力再建型とは、その名のとおり、自社の収益を原資として借金を返済し、自力で再建を図る方法です。
収益が安定していることが条件ですが、スポンサーをつけることが難しくても手続できる可能性があります。
清算型
清算型とは、事業の全部または一部を受け皿となる会社に譲渡したうえで、旧会社を清算し、受け皿となる会社において再建を図る方法です。
もともとの会社は、事業譲渡により得た対価を借金の支払いに充てます。清算型とはいえ、会社のすべてが失われるわけではありません。
民事再生手続が開始されたあとに、裁判所の許可を受けて、事業譲渡を行うことになります。
民事再生法と会社更生法の5つの違い
民事再生法に似た法律として会社更生法があります。
いずれも会社を建て直すことを目的としている点で共通していますが、会社更生のほうが、多くの人が関わることを想定しているため非常に複雑な手続となっています。
主な違いは以下の5つです。
- 申請手続ができる対象者
- 財産の管理者と経営陣の扱い
- 担保権実行の可否
- 返済期間
- 手続に要する時間
それぞれについてご説明します。
申請手続をできる対象者
民事再生法と会社更生法では、手続できる主体が異なります。
| 民事再生法 | 個人・法人(会社の種類は問わない) |
|---|---|
| 会社更生法 | 法人のなかでも、株式会社のみ |
財産の管理者と経営陣の扱い
民事再生では原則として、もともとの経営者が業務遂行権や財産管理処分権を行使できます。
ただし、なかには管財人や保全管理人、監督委員、個人再生委員などが任命されることもあります。
会社更生では、その時点での経営陣はすべて交代することが原則です。裁判所により更生管財人が選任され、更生管財人は会社の財産や業務を管理すると同時に、経営を行っていくことになります。
債権者による担保権実行の可否
民事再生では、民事再生を行っている会社の債権者が原則として自由に抵当権などの担保権を実行し、お金を回収することができます。
ただし、「この財産が競売にかけられてしまっては、事業を継続できなくなってしまう」などの場合には、「担保権の実行手続の中止命令」の申立てなどにより、担保権の実行を防ぐ手当ても講じます。
会社更生では、債権者が担保権を実行することはできません。更生管財人による担保目的物の評価に基づいて、財産を処分するなどして得た配当などを受けります。
返済期間
民事再生の返済期間は、5~7年(最長10年)が一般的です。
会社更生手続は、大手の企業が採る手続であるため、借金の総額も高額であることが多く、10年を超えることも珍しくありません。
手続に要する時間
民事再生では、裁判所に申し立てたあと、再生計画案について認可が出るまでにはおよそ半年ほどかかります。
一方、会社更生では、申立後に更生計画案の認可が出るまで数年かかるケースもあります。
民事再生のメリットとデメリット
民事再生にはどのようなメリット・デメリットがあるのかを解説します。
民事再生を申請するメリット
民事再生を申請するメリットは以下の2つです。
- 事業を継続できる
- 経営陣が交代しなくてもよい
民事再生は、事業を継続しながら、事業を再建することを目的としています。
また、会社更生とは異なり、経営陣が交代せず、現状の経営陣で再建を図れます。ただし、監督委員が付く場合には、その監督に服する必要があります。
民事再生を申請するデメリット
民事再生を申請するデメリットは以下の2つです。
- 債権者から担保権を実行される可能性がある
- 世間、取引先、顧客、従業員などからの信用を失う可能性がある
担保権を実行されると、不動産などの担保目的物を失うことになります。
なお、信用を失う可能性があることについては、経営状況の悪化がそもそもの原因なので、必ずしも民事再生のデメリットだとはいえません。
民事再生法に基づく民事再生の申請費用
民事再生は、手続が煩雑で、高度な法律知識を要するため、弁護士に依頼するのが一般的です。そのため、裁判所への予納金、申立実費のほかに、弁護士費用が必要となります。
まず予納金は、負債総額に応じて金額が異なります。
たとえば高松地裁では、次のように決められています(2019年10月1日時点)。
| 負債総額 | 基準額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 200万円 |
| 5,000万~1億円未満 | 300万円 |
| 1億~5億円未満 | 400万円 |
| 5億~10億円未満 | 500万円 |
このように、借金の総額が多額になればなるほど、予納金の額も上がります。
参考:民事再生事件の手続費用一覧 高松地方裁判所|裁判所 – Courts in Japan
法人の再生の場合、弁護士費用も高額であり、負債総額が1億円以下であっても、着手金と成功報酬金で合わせて800万~1,000万円程度かかることが一般的です。
ほかにも、申立実費として収入印紙代や郵券代もかかります。
民事再生法に基づく民事再生の申請や手続の流れ
では、民事再生がどのように進められていくのか、流れを順番に解説していきます。
民事再生法による民事再生の申立て
通常、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に民事再生の申立てをすることになります。
再生手続の開始決定
申立てから2週間程度で、裁判所により再生手続の開始決定が出て、具体的に手続が開始されることになります。
債権届出、認否貸借対照表と財産目録の提出
債権者は、民事再生手続に参加するとともに債権届を提出します。債務者はそれぞれの債権者や債権額についての認否を行います。
債務者は、保有財産の評定を行い、貸借対照表と財産目録を裁判所に提出します。
| 貸借対照表 | 会社の財務状況が記載されているもの |
|---|---|
| 財産目録 | 会社が保有する財産や負債を区分、種類ごとに記載しているもの |
再生計画案の提出、認可
再生計画案とは、借金をどのようにして返済していくかを定めたものです。
その作成にあたっては、各債権者から提出された債権届を踏まえ、また、大口債権者への返済方法をどのようにするかを重点的に考慮することが大切となります。
再生計画案を提出したあと、債権者集会が開かれます。出席した債権者の過半数の同意、かつ、債権総額の2分の1以上の債権者の同意により、債権者集会で再生計画案について可決されると、裁判所により再生計画案の認可が下りることになります。
このように、民事再生は手続が煩雑で、問題なく手続を終えるためには高度な法律知識が必要です。
民事再生を利用しようかお悩みの経営者の方は、企業法務を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。
※現在、アディーレ法律事務所は法人に向けた民事再生のご相談・ご依頼を受け付けておりません。個人で民事再生を検討している方は「個人再生」のページをご覧ください。
お客様の声
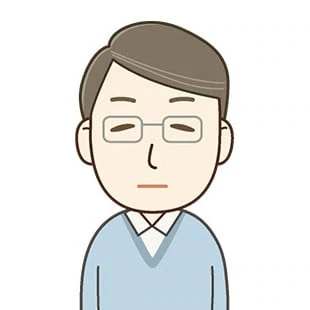
困った時は専門の人の手助けに頼るしかない!
- 個人再生
- 40代
- 男性

たくさんの方に親身になって悩みを聞いてもらえました
- 個人再生
- 40代
- 女性
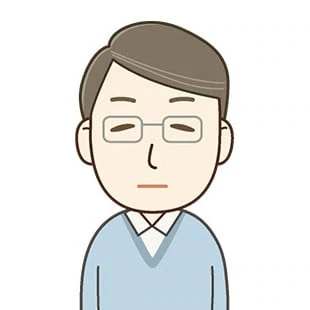
2回目の個人再生でしたがきちんと対応してくれました
- 個人再生
- 40代
- 男性
このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。